時の図書館 Vol.1
沈黙の春
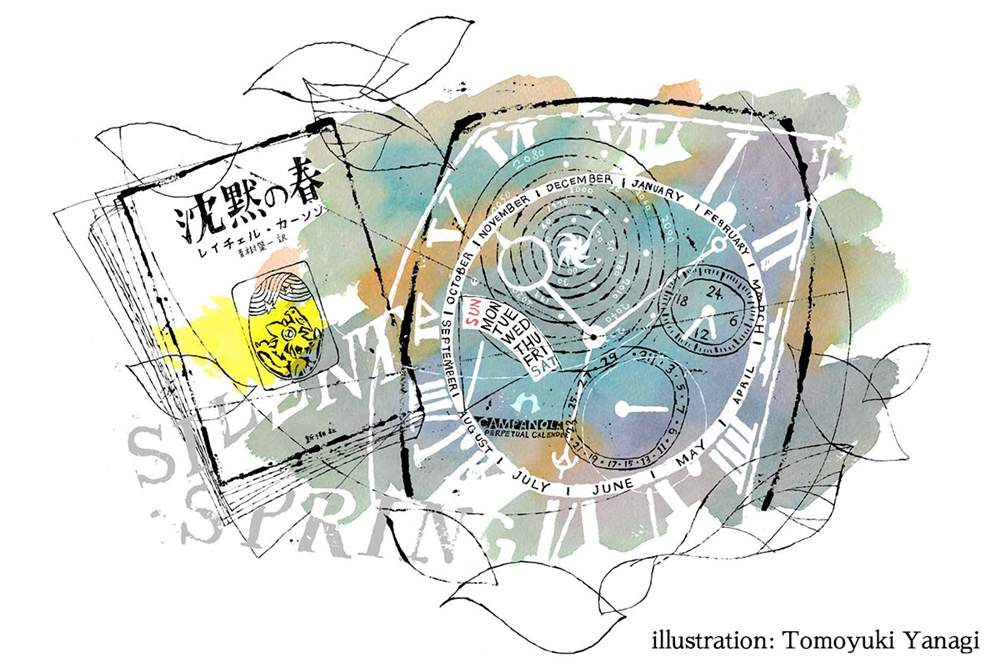
illustration: Tomoyuki Yanagi
わたしのカンパノラはパーペチュアルカレンダー付き。1900年3月1日から2100年2月28日の間の、任意のいち日を呼び出すことができる。さて、今日はどこに時間旅行してみよう。わたしは、1964年4月14日に行ってみることにした。調べるとその日は火曜日であることがわかる。緯度が高い地方ではまだ完全な春とはならず、すこし肌寒い、くもりの日だったのではないだろうか。なぜかそんな気がした。
カンパノラの文字板の上には、細かい数字が放射状に吹き出して並んでいる。まるで銀河系外の星雲みたいだ。現行のグレゴリオ暦では、今年(2020年)のように4で割り切れる年をうるう年としているが、1900年や2100年のように100で割った商(答え)が、4で割り切れない年は、うるう年とせず平年と定めている。この規則性から、1901年から2099年までのあいだは4年に一度、うるう年があり、一週間は7日の曜日を繰り返すので、カレンダーは、4と7の最小公倍数、つまり28年周期で繰り返される。それゆえ、カンパノラのパーペチュアルカレンダーの目盛も28年周期の同心円状に配置されていて、年針が示す延長線上の年はすべて同一のカレンダーとなる。つまり、1964年のカレンダーは1992年と同じ、そして今年2020年とも同じなのである。
わたしは、かつてニューヨークで、それからボストンで研究生活をしていたことがある。海外生活とはいっても華やかさとは無縁。研究者の卵だったわたしは精神的にも経済的にも余裕がなく、毎日が必死だった。早朝から深夜まで実験室で研究にあけくれ、やっとのことでボロアパートに寝るためだけに帰った。
それでも、あるとき実験室を離れるほんのわずかな機会があった。泊まりがけの研究会が開催され、参加を許されたのだった。場所はマサチューセッツ州ケープ岬の付け根、ウッズホール。ニューヨークとボストンの中間にある小さな街だ。バスを乗り継いで出かけた。そこにある海洋生物学研究所が会場だった。茶色の石積みの建物が並ぶ。敷地は、海に向かって開いた美しい入江に面していた。わたしは海を見渡せるところまで歩いていった。季節は春先。大西洋は冷たく光っていた。海風が強い。
ポケットに深く手を入れて、上着の前を押さえながら、わたしは、ずっと以前、同じこの海を眺めたはずの女性のことを考えた。
もともと書くことを仕事にしたかった彼女は、ふとしたきっかけから生物学の勉強をはじめ、ここウッズホール海洋生物学研究所の夏季研修に参加した。内陸で育った彼女は広い大西洋を初めて見た。それが彼女を捉え、生涯、彼女を放すことがなかった海との出合いとなった。
のちに書かれたレイチェル・カーソンの処女作『潮風の下で』の冒頭は、こんなフレーズで始まっている。
〈その島は、静かに忍び足で東の入り江を横切ってきたたそがれよりもほんのわずか深い影に包まれていた。島の西側にある湿った狭い砂浜は青白くきらめく空を反射し、その輝きは島の砂浜から水平線に向かって明るい道筋をつけていた。〉(上遠恵子訳)
彼女の文章は抒情に満ちあふれ、それでいて抒情に流されることがない。いつも整合性を保ち、正確で科学的な解像度を追求していた。海の生態と生命のダイナミズムを鮮やかに描いた彼女の作品に世間の注目が集まった。彼女はこう語っている。「私の文章に詩があるのではなく、海に詩があるのです」。センス・オブ・ワンダーという言葉を広く世に知らしめたのも彼女だった。子どもたちに失ってもらいたくない感性がある。それはセンス・オブ・ワンダーだと。直訳すれば、自然の精妙さに驚く心。上遠訳では、“自然に対する畏敬の念”。
名門ジョンズ・ホプキンス大学院で生物学を修めた彼女にはずっと心を悩ませていた懸念があった。時は1950年代から60年代初頭。化学の時代が到来し、農薬や殺虫剤が大量に散布されはじめた。
彼女は丹念にデータを集め、解析し、殺虫剤DDTや有機リン剤の乱用が、時間と空間を経て、生態系のバランスにどのような影響をもたらすか、考察を進めた。殺虫剤は害虫だけを殺すわけではない。あらゆる虫を殺す。虫が死ねば、種は実らない。あるいは虫を餌としていた魚や鳥が影響をうける。ある生物群の変動は別の生物群に影響する。薬物は食物連鎖を通して濃縮される。魚が消え、小鳥も歌わない。春は沈黙することになる。
こうしてレイチェル・カーソンの『沈黙の春』が完成した。1962年のことだった。環境問題に警鐘を鳴らした歴史的な名著。その核心はこうだ。環境は生態系の動的な平衡に支えられており、その平衡を乱す人為的な行為は、時間的・空間的な壁を超えて大きなリベンジとなって人間をも脅かすことになる。
実は執筆当時、すでに彼女は病を得ていた。進行ガンが身体を蝕んでいたのだ。「わたしを支えるものは、最後にできあがるべき本が、ゆるぎない基礎の上に築き上げられていったのだという澄み切った内面的な確信です」。そう彼女は述べている。
化学メーカーや圧力団体などが一斉に反撃を開始した。非科学的な誇張である。独身女のヒステリックな言説だ。それらは口汚く、すさまじさを極めた。
しかし彼女は全くひるまなかった。なぜなら彼女は何も誇張しなかったし、ヒステリックでもなかったから。彼女は生命のありようを正確に記述しようとしたのだ。やがて『沈黙の春』に込められたメッセージは広く人々に共有され、政府の環境行政を動かし、制度や規制を強化する方向へと導いていくことになる。現在の地球温暖化に対する危機感もこの流れの上にあるといえる。4月14日はレイチェル・カーソンの命日。28年の周期を2回経た今もなお、彼女の地球環境へのメッセージは、強まりこそすれ少しも色褪せることがない。
沈黙の春
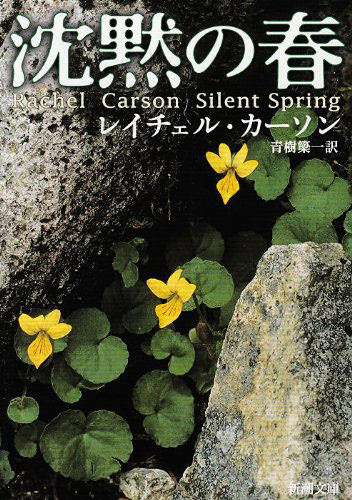
(著者)レイチェル・カーソン著、青樹簗一訳
(出版社)新潮文庫
(価格)710円+税