時の図書館 Vol.12
時空を超えた時間の円環をつなぐもの
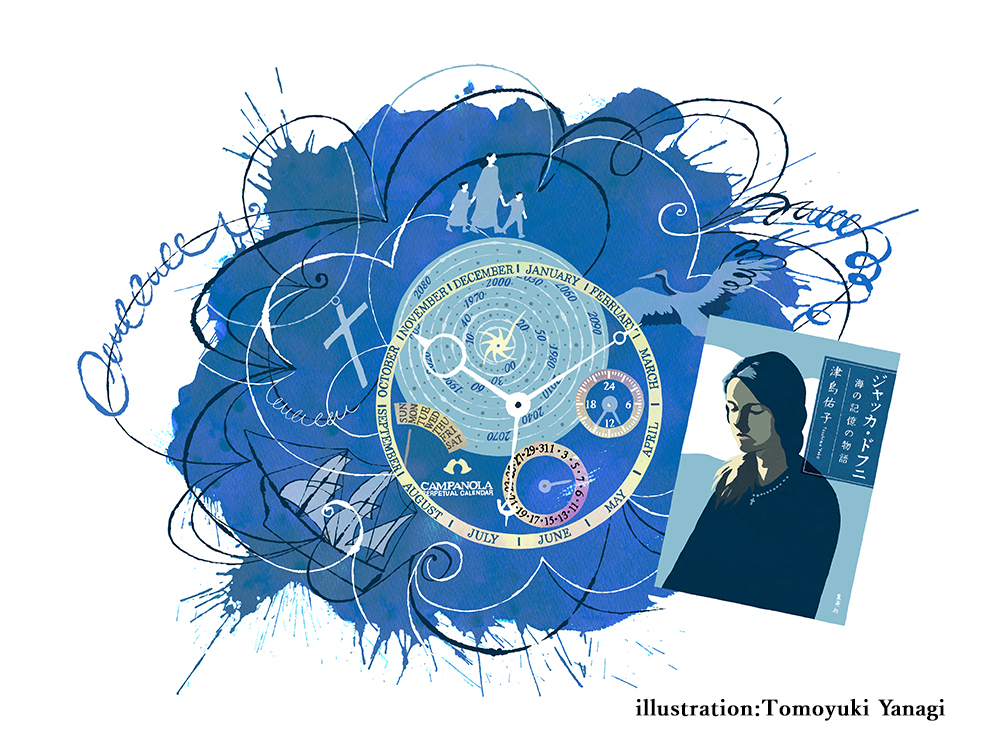
illustration: Tomoyuki Yanagi
作家・津島佑子が惜しまれつつこの世を去ったのは2016年2月のことだった。死因は肺がん。68歳だった。『光の領分』(野間文芸新人賞)、『夜の光に追われて』(読売文学賞)、『火の山―山猿記』(谷崎潤一郎賞)など、作品は多くの文学賞を受賞したほか、多数の言語に翻訳され、シンポジウムに招かれるなど国際的に活躍した。1991年、湾岸戦争が起きると柄谷行人、中上健次、田中康夫らとともに「湾岸戦争に反対する文学者声明」を発表した。また、東日本大震災のあとには国会周辺で開催された反原発デモに参加するなど、文学者として積極的な政治参加を行った。
津島佑子の追悼記事を、柄谷行人がこんなふうに書いている。
「彼女は、私生児や孤児、障害者、少数民族、動物のようなマージナル(周縁的)な存在について書く作家であった。虐げられたものへの共感と深い愛情をもつ作家であった。そして、そのために世界各地で活動した。たとえば、フランスの大学でアイヌ文学について講義したこともある。」
「日本では知られていないが、津島佑子はノーベル文学賞の有力な候補者であった。それに最もふさわしい多様な作品を書き、国際的な活動をしていた。もう少し長生きすれば、受賞したであろうから残念である。」
(朝日新聞 2016年2月23日朝刊)
そして柄谷は同じ記事の中でこうも記している。
「『ジャッカ・ドフニ』となると、世界文学史において類を見ないような作品である。」
今回の「時の図書館」は『ジャッカ・ドフニ』を取り上げたい。時間と記憶をめぐる壮大な物語がテーマだからである。『ジャッカ・ドフニ』は、2015年に文芸誌「すばる」に連載された後、2016年5月に単行本として刊行され、津島佑子の遺作となった。
周知のとおり、津島佑子は作家・太宰治の娘である。太宰は、津島佑子が一歳のとき、愛人とともに玉川上水に身を投げて自殺した。津島は小さい頃から、なるべく他人から父のことを聞かれないように、と願いながらすごした。長じてものを書くようになってからも、できるだけ自分が太宰治の娘であるという事実を察せられないようしていた。しかしどんなに隠しても、彼女のストーリーテリングの妙やリズミカルな文体は父から譲り受けた才能であるという気がする。
“ジャッカ・ドフニ”とは何であり、世界文学史上、類を見ないような作品とは一体どんなものなのであろうか。
『ジャッカ・ドフニ』はとてつもない規模の時間と空間の広がりを持つ小説である。副題に「海の記憶の物語」とあるように、さまざまな海の記憶の往還が、複雑な様相を持って行きつ戻りつを繰り返す。その構造を読み解いていきたい。
小説は「二〇一一年 オホーツク海」と題された序章から始まる。
著者を仮託するように思える話者としての「わたし」は、大震災が東日本を襲った年の9月の終わりに、ひとり北海道オホーツク地方を旅する。荒涼とした海を見渡していると、カムイ・ユカラの歌が聞こえてくる。
「ノックルンカ 今年という年は
ノックルンカ ひどい山津波と
ノックルンカ はげしい沖津波とが
ノックルンカ 両方から襲来
ノックルンカ するであろう。……」
(『ジャッカ・ドフニ』7-8ページ、以降の引用は全て単行本版に準拠)
カムイ・ユカラとは、神の歌という意味である。アイヌに伝承される独特の歌謡で、サケヘと呼ばれる意味のないリフレインがついている。この歌のサケヘは、ノックルンカ、である。
この歌は、もちろん東日本大震災を直接歌ったものではなく、古来、アイヌに伝承されてきたものだ。しかし、歌は不可避的に、過去と現在をつなぐ。この小説では、歌が、悠久の時間を接続する媒体として繰り返し引用されることになる。
これを聞いて「わたし」は思う。
「津波で失われた多くの子どもたちの命から、わたし自身が引きずり続けている個人的な経験が呼び起こされた。」
(10ページ)
「わたし」は、アイヌの出自を持つ若い青年ガイドの案内でシレトコの森を散策する(本書では、シレトコ、アバシリなど、地名はカタカナで表記される)。カムイ・ユカラはその青年が教えてくれたものである。ところがほどなく、この旅の記録が、2年後の「今」から思い返されていることが明らかにされる。ここにすでに記憶をめぐる揺らぎがある。2年前の記憶はもう遠い過去になっているのだ。
「旅館の玄関を恨めしげに見つめながら、雨混じりの風に吹かれてたたずみつづける、すでに六十歳を過ぎ、しょんぼりと疲れた風情の女の姿が、二年後のわたしの脳裡に遠く浮かぶ。どうして、こうも遠く感じてしまうのだろう、ごく最近の記憶だというのに。」
「いくつもの記憶の領域があって、なかには、自分からできるだけ近づきたくない領域がある。」
(ともに12-13ページ)
そして小説の構造もきしみ始める。突然、話者の人称が変わるのである。「わたし」は、「あなた」と呼びかけられる存在となって話が展開されていくのだ。
「アバシリという土地は、あなたにとって二十六年ぶりで、当時、北方民俗資料館はまだ存在しなかった。二十六年という年月は、ひとりの人間が生きる時間から考えても十分に長い。」
「二十六年前のあなたはまだ若く、八歳になったばかりの、ダアと呼んでいた子どもを連れて、アバシリを訪れた。」
(ともに19ページ)
2011年から見て、26年前とは、1985年のことである。「わたし」は「あなた」と呼ばれることによって、現在の私が、過去の自分と対話することになるのである。
「あなた」は、時間について思いを巡らす。
「時間が流れるとよくひとは言うけれど、生きている人間がそのような流れを実際に見届けることはできない。現在がどこまでもつづき、現在しか見えず、背中のうしろには、いつもなにかがうごめいているのを感じつづけ、けれど振り返れば、そんなものはすっと消えてしまう。なにひとつ、現在のあなたの手もとに取り戻せない。」
(19-20ページ)
今、生きていること以外、時間の実在性を知る手がかりは何もないことが表明される。
「あなた」は、26年前、ダアと一緒に、ジャッカ・ドフニを訪問したことを語る。ジャッカ・ドフニとは、サハリンのアジア系少数民族ウィルタの言葉で、「大切なものを収める家」という意味である。ウィルタ出身のゲンダーヌ、日本名・北川源太郎が、トナカイ遊牧民ウィルタの文化を保存するため建造した民族資料館だった。
ジャッカ・ドフニは、「拍子抜けするほどつつましい広さで、部屋の真ん中にはウィルタ式――それはアイヌの形式とも共通しているけれど――の大きな囲炉裏が切ってあった。壁際には、木彫りの守り神や木弊、満州族の服に似た民族衣装、楽器、トナカイたちに曳かせるソリ、手作りの生活用品などが、一見無造作に置かれていて、ダアはおもちゃの家に迷いこんだとでもかんちがいしたのか、すっかりはしゃいで、貴重な陳列物に手を伸ばそうとしたり、囲炉裏のまわりをぐるぐる走ろうともする。」(22ページ)
「あなた」が必死にダアを止めようとする場にたまたま居合わせたゲンダーヌさんは、母子に優しく言う。
「いいんですよ。」
「そこら辺に置いてあるものには、どんどん触ってください。ここは、そういう方針なんです。……ねえ、触りたかったら触りなさいね。」
(22ページ)
そして、ゲンダーヌさんは、建物の入り口に佇む母子の記念写真を撮影してくれる。「あなた」は、これがダアの遺影になることをこの時点ではまだ知らない。
「引きずり続けている個人的な経験」「できるだけ近づきたくない領域」とはこのことだった。しかし「あなた」は死という言葉を使うことをしない。かわりにこう記す。
「それから七ヶ月後に、ダアはあなたの時間から消え去った。」
(21ページ)
冷たい雨が降りそぼる中、人気のない北方民族資料館を訪れた「あなた」の記憶は、だんだん不確かなものになる。タクシーの運転手が話してくれた思い出話では、ゲンダーヌさんが亡くなったのはジャッカ・ドフニが1978年に完成してから6年後のこと。「あなた」とダアが、夏休みにそこを訪問したのは26年前のこと。計算が合わない……。
序章は、次のような謎めいた文章で終わる。
「九月のシレトコ、そしてアバシリで、あなたはセミの鳴き声を聞かなかった。セミはすでに、神々の村に戻っていたようだ。」
(39ページ)
セミとは一体何の隠喩だろう。それが明らかになるのはずっとあとのことである。
序章が終わったあと、『ジャッカ・ドフニ』は意外な展開を見せる。一挙に時空が、なんと400年もワープするのだ。
時は、1620年前後、登場人物は、チカ(チカップ)とジュリアン。チカの母はアイヌ人の女、父は砂金を求めて北海道に渡った荒くれ男だった。ジュリアンは日本人の少年。キリシタン迫害で、一族ともどもツガルに流される。神父(パードレ)になるべく学問を修めることを志している。幼くして孤児となったチカは、旅芸人の一座に拾われてさすらうが、偶然、ジュリアンと宣教師の一行と出会い保護される。以降、チカはジュリアンを兄のように慕う。
チカとジュリアンは、安住の地を求めて、宣教師や隠れキリシタンたちの手助けを受けながら、ナガサキ、ヒラドを経て、アマカウ(マカオ)に向かう船に乗る。
チカの口からは、ハポ(母)が歌ってくれたアイヌの子守唄が少しずつこぼれ出す。
「ルルル、ロロロ、モコロ、シンタ、ランラン、ホーチプ! ホーチプ!」
(『ねんねのお舟が降りてくる、降りてくる、そら漕げ、そら漕げ(55ページ)』)
それはチカが自分の出自を取り戻すことに繋がっていく。苦しく長い船旅に耐えた末、明るく晴れ渡った新天地、マカオの港に到着するところで第一章が終わる。
ここで再び、話は「あなた」とダアの物語に戻る。1985年、二人は北海道オホーツクを旅する。楽しい夏休みの記憶。
ダアは、原生林の中を飛ぶ鳥に興味を示し、アマガエルに声を上げる。ダアは生き物が好きなのだ。ガラパゴス島にあこがれている。
ここでも時間の記憶が行き来する。「あなた」はかつて学生時代、北海道を旅し、ハクチョウを見たことを思い出す。ダアにもハクチョウを見せてあげたい。
ダアと「あなた」は、ジャッカ・ドフニを訪問し、ウィルタ人ゲンダーヌさんと会う。「あなた」は、ダアに説明する。
「もっと北のほうにサハリンという大きな島があって、そこに住んでいたウィルタ、ニブヒというひとたちも日本の戦争に兵隊として使われて、死んじゃったんですって。」
(215ページ)
戦後、ゲンダーヌさんは、少数民族の戦争被害補償を日本政府に求めて国と戦ったが受け入れられなかった。日本軍に使い捨てられた悔しさと情けなさを、せめて慰霊碑と民族資料館の形で残さずにはいられなかった。
一方、戦争が始まる前の、ウィルタの人たちの暮らしは、厳しいながらも自然とともに生きる平穏なものだった。
「冬のあいだ、タライカ湾に注ぐポロナイ川は凍結し、子どもたちは手作りのスケートで遊ぶ。ひとびとは歩いて、あるいは、トナカイや犬が引くソリで、川を渡る。春になり、その氷が解けはじめるころ、ゲンダーヌさんは生まれた。
子どもたちにとって、解けはじめた氷のうえでスケートをするのは、とりわけおもしろい遊びだった。薄くなった氷が割れ、毎年何人かが水に落ちてしまう。ゲンダーヌさんも二度落ちたことがある。穴に落ちたら、アザラシのように頭だけを出して、動かずに助けを待つ。へたに動けば、穴が広がって、取り返しのつかないことになる。」
(222ページ)
ゲンダーヌさんの少年時代の思い出は、ダアをめぐる記憶に重なる。
ダアと過ごした東京の都会ぐらしの断片。ダアは思いがけない場所に自然を見つけた。山手線の土手の柵をくぐり抜けた向こうにある水路にいるザリガニ。公演で見つけてきたトカゲやヒキガエル。郊外の小川で捕まえたオタマジャクシ。
やがて「あなた」の思いはあてどのない後悔へと集約されていく。
北海道旅行から戻って7ヶ月が経過したある日曜日の夕方、なぜ「あなた」はダアをひとり残して、ほんの短い時間だったにせよ、外出してしまったのか。あと10分早く戻っていたなら。そもそもなぜマンションの9階に住むことになってしまったのか……。
『ジャッカ・ドフニ』は、三度、北海道オホーツクを旅した「あなた」の記憶が、2011年、1985年、1967年、と逆順に置かれた間を、1600年代を通して、日本海、南シナ海、ジャワ海を生きたチカの物語が配される構造をとる。
そして読者は、時間も空間も遠く離れた世界と人間が互いに密接に繋がっていく深淵で壮大な体験を味わう。時空を繋ぐものは海である。海は世界を隔てるものではなく、引き合わせる媒体としてある。そしてその海を渡って聞こえてくるものは歌だ。
歌がもたらすものは、抑圧されたもの、疎外されたもの、周縁に追いやられたものたちへの時を超えた記憶である。
和睦をよそおいながら、和人から毒をもられて惨殺されたアイヌのひとたち。日本人として戦争に招集され、使うだけ使われたあと打ち捨てられ、何の保護も補償も受けられなかった北方少数民族ウィルタやニブヒのひとたち。迫害を受け、潜伏や逃亡のあげく捕らえられて処刑されたキリシタンたち。「あなた」は、伝承歌謡の切れ切れの断片を手がかりに思いを馳せる。そして悲しみを共有する。
アイヌの出自を持ち、キリシタンとなったチカップは二重の疎外を受ける。日本人からの疎外。信教上の疎外。それだけではない。マカオに逃れたあとも、女であるがゆえに、正規のキリスト教教育の道に進んだ兄しゃまジュリアンとは離れ離れになり、洗濯女として日々の労働に消耗せざるを得ない生活を送る。それでもチカは自分の由来を考え続ける。
チカップのまわりにも、疎外された者たちがいる。秀吉の朝鮮出兵時代に捕らえられ日本に連れてこられた男性。彼はキリシタンとなり洗礼名ペトロとなり、チカップとともにマカオに逃れる。マカオでも様々な人たちに出会う。日本人の母とナポリ人の父とのあいだに生まれた少年ガスパル。アフリカから奴隷として連れてこられた女性イブ。
彼ら彼女らは、いっときマカオで、貧しいながらも平穏な日常の暮らしを得る。が、歴史の潮流は安住を許さない。ヨーロッパ諸国の衝突と争乱がマカオにも押し寄せ、日本から逃れてきたキリシタンたちもこの場にとどまることができなくなる。
チカップは、修道院に残る決意をしたジュリアンと別れ、ジャワに向かう船に乗る。
ジャワのバタビアに渡ってからのチカップの半世紀に及ぶ消息は、チカップが代筆者の助けを借りて、ジュリアンに宛てた3通の手紙、という形式を取る。むろんジュリアンがどこにいるかはわからず、この手紙が届く可能性は極めて低い。だから手紙はチカップの独白、という要素が強い。
1639年、一通目の手紙では、マカオでジュリアンと別れてから9年が経過したときに書かれたもの。チカは24歳になり、現地の人と結婚し、二人の子どもがいる。チカはいまだに自分の出自にこだわり続けている。子どもにもアイヌの言葉で名前をつけた。上の娘はレラ、下の息子はヤキ。レラはかぜ、ヤキはせみ、という意味である。チカは、子どもたちにアイヌの歌や言葉を教える。
「きりしたんとしてよりも、アイヌのおなごとして、チカップは生きとうよ。そいが、チカップのねがいや。
兄しゃまはわかっとくれるよね。」
(370ページ)
1643年の二通目の手紙で、チカは重大な告白をする。チカは、オランダの探査船が、バタビアから日本のえぞ地に向けて出港するという噂を聞きつける。チカはこの船に、10歳と9歳になったレラとヤキを密航させ、自分のふるさとえぞ地に送り込むことを思いつく。
「あんたらのうまれたバタビアはオランダという国の支配地で、まわりにはバンテン国とかマタラム国などのジャワ人のくにがある。何年たっても、あんたらはちゅうとはんぱなたちばなんや。あんたらにとってのほんらいのばしょは、えぞ地しかなかよ。えぞ地は、ふるくからずっとアイヌの土地なんやから。」
(392ページ)
この計画を打ち明けられたレラとヤキは最初驚くが、まもなく母の言葉を受け入れ、えぞ地行きを決意する。チカは水夫になけなしのお金を渡し、密航の手はずを整える。いったん乗り込んでしまえば、もうこちらのもの。子どもたちが好奇心から勝手に乗り込んだことにすれば、船長も子どもたちを追い返すことも、海に突き落とすこともできないはず。
この計画はチカの夫に秘密で行われた。突然、子どもたちが行方不明になり、夫は半狂乱になる。チカは、子どもたちは神隠しにあった、と言って嘘をつきとおす。
最愛の子どもたちを手放す。このシーンは、この小説にとってハイライトといってよい。チカは希望を持って子どもたちを手放した。子どもたちが本来属するべき場所へ送り帰した。つまり、何かを手放すことが、喪失ではなく創出でありうるということが示される。
1673年の三通目の手紙は、二通目の手紙が書かれてからかなりの歳月が経過したあとのもの。年をとったチカは病床にある。しかしその心は静かな安寧に満たされている。戻ってきた水夫を探し出して消息を確かめたところ、レラとヤキは、えぞ地についた探査船から逃げ出したことを知った。探査船の乗組員は誰もあとを追ったりしなかった。
あらゆるものは流れゆく。
流れが線形であるならば、それは一端から他端への消失となる。しかし、流れがもし円環となるならば、全体として失われるものはない。ただ姿を変えながら受け渡されていくだけだ。生は絶えず他者に受け渡され、死は生となる。
チカップは、手紙にこんなふうに記す。
「兄しゃま、じかんがたてば、……
さまざまなことがうつりかわっていくんやね。
うつりかわって、なにひとつもどらん。
けんど、もともと、
ながれすぎていくものなんかなかったんや、ともおもいます。……
このせかいのなんもかもが、
ぐるぐるとまわりつづけ、
風がふき、川や海のながれはとまらず、
むすうの命がきえてはあらわれ、……
そんなら、なんにも
ながれとらんのとおんなじになります。」
(415ページ)
レラとヤキはその後、どうなっただろう。おそらくえぞ地のアイヌたちにあたたかく迎え入れられただろう。そして、レラとヤキは母の物語を熱心に語った。その物語はやがてアイヌの歌となり受け継がれ、いつしかあなたのものへ届くかもしれない。歌は、最愛の子どもを手放したあなたの心を癒やしたはずだ。
最愛の子どもを手放さざるを得なかった母親の苦悩。これは作家・津島佑子の物語でもある。津島は20代の前半、最初の結婚をし、娘を生むが後年、夫とは不仲になり離婚する。その後、新たなパートナーを得るが、制度上の理由から婚姻しないまま長男をもうける。しかし長男は1985年3月、8歳のときに急死してしまう。『ジャッカ・ドフニ』の語り手が呼びかける「あなた」には、津島自身の体験が色濃く投影されている。そして『ジャッカ・ドフニ』は、津島自身の喪失と創出の物語でもある。
最後に、「1967年 オホーツク海」と題された短い章が、エピローグ風に置かれる。
二十歳になった年の春「あなた」は、北海道をひとり旅する。均一周遊券で移動し、ユースホステルに泊まる。クシロの湿原で凍えながらタンチョウヅルを見る。シーズンオフのみやげ物の店には誰もいない。アイヌの歌、と書かれた小さな本を見つける。値段がわからず、適当な金額を料金箱に入れる。
本にはこんなことが書かれていた。
「『アイヌ』は人間という意味のアイヌ語です。日本人は隣人『シサム』と呼ばれます。この美しいホッカイドウはアイヌの土地、『アイヌ・モシリ』でした。」
(441ページ)
「あなた」はこの言葉を繰り返しつぶやく。アイヌは人間。わたしはシサム。ここはアイヌ・モシリ、人間の大地。アイヌの歌が切れ切れに聞こえてくる。「あなた」は霧に閉ざされたマシュウ湖を見に行く。
物語の最後は、アイヌの歌を口ずさみつつ、アイヌのこと、ウィルタやニブヒのことをもっと知りたいと考えながら、「あなた」の印象的な描写で幕を閉じる。
「シサムのあなたは背中のリュックを背負い直し、海岸沿いに歩く。海の歌声は、そのあなたを追ってくる。
フアオーウ テパカン、テパカン
フアオーウ エマトゥネ
フアオーウ シルポック
フアオーウ サンオタ カタ
フアオーウ エチス リミムセ」
(458-459ページ)
彼女が「背負い直した」ものとは何だろうか。それは、何百年にも渡って語り継がれてきた海の記憶に他ならない。そして、このあと彼女が背負うことになる未来の記憶への予感でもある。こうして海の記憶の物語は、果てしのない円環を巡る生命の海流となる。
ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語


(著者)津島佑子
(出版社)集英社
(価格)文庫版上巻 770円(税込)、下巻814円(税込)