時の図書館 Vol.6
ビーグル号航海記
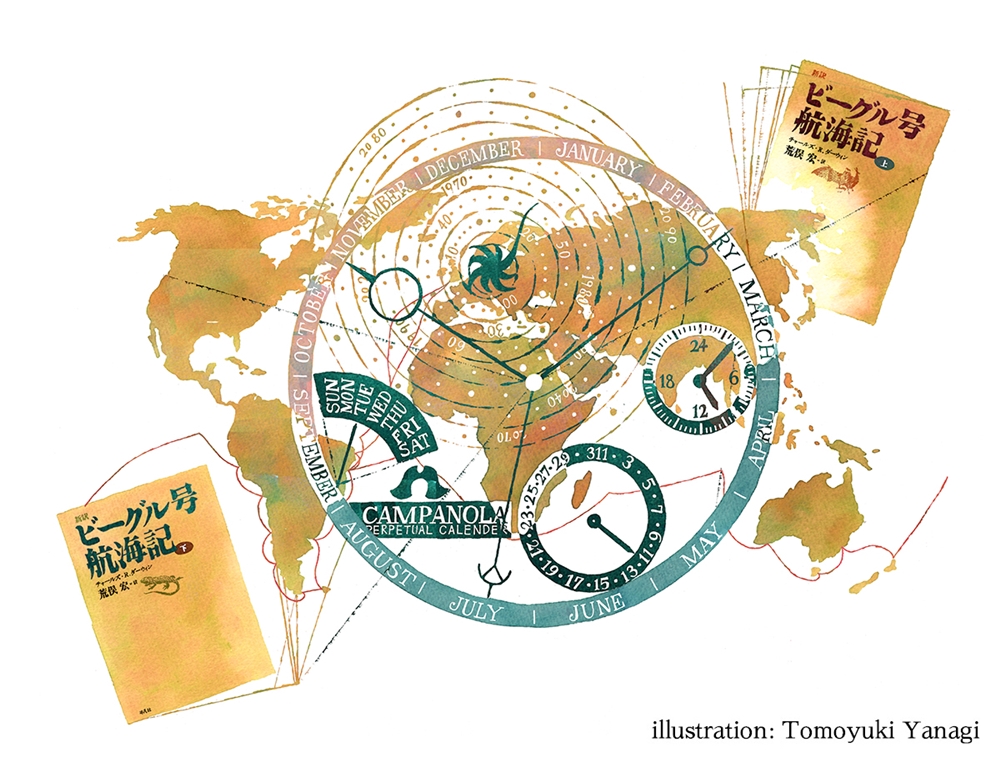
このほど私は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のプロデューサーの一人に選出された。2025年、大阪の海浜部に造成された夢洲(ゆめしま)地区に招致されることが決定した国際博覧会である。この万博のテーマ館パビリオンの企画・立案をするという役割だ。これはある意味で恩返しとでも言うべき責務になるように思う。
というのも、万博といえば、私たちの世代にとっては、なんといってもEXPO’70だからである。1970年、同じ大阪の地で開催された万博に大きな影響を受けた。
当時、私は10歳。世相は、安保闘争や東大紛争が起こり、御茶ノ水や駿河台の学生街には立て看が立ち並び、東京の空には、いつもヘリコプターが飛び回って、騒然としていた。が、少年にとっては、上の世代が何にそれほど怒っているのかよくわからなかった。むしろ、新幹線が開通し、アポロが月に行き、未来都市が具現化されたEXPO’70に限りない明るい希望を感じた。
親にせがんで、東京から出かけて行った。最寄りの駅からバスに詰め込まれ、千里丘陵の竹林を抜けていくと、向こうの方に、スタイリッシュな建物や尖塔、ドーム群などのスカイラインがまるで蜃気楼のように浮かび上がってきた。私の興奮は極点に高まった。
EXPO’70の一番人気は、アメリカ館だった。それは現代で言えば東京ドームを先取りしたような、白い空気膜構造で覆われた楕円形の巨大な建築だった。内部に柱はなく、当時の宇宙工学の粋を結集して設計されたものだった(ガラス繊維とワイアロープだけで屋根を支え、内部の空気圧で膨張させていて、たとえ大量の降雪があっても支えられるとされていた)。そして内部の目玉展示は、その前年、アポロ8号が月面着陸に成功し持ち帰ってきた「月の石」だった。それは褐色の溶岩のような鉱物で、支持台のガラスケースの中に燦然と輝いていた。人類が地球以外の天体から持ち帰ったはじめてのサンプル。夢想は宇宙の彼方にひろがっていった。
どのパビリオンも長蛇の列。到底、一度の訪問では見きれないので、春と夏、2回も出かけていった。
これを最近知人に話したら「それは福岡さんがボンボンだったということですよ。2回も連れて行ってもらえるなんてすごく贅沢なんです。漫画『20世紀少年』を見てごらんなさい。行きたくてもいけなかった少年が、行ったと嘘をつくんです」と言われてしまった(念のため釈明すれば、わたしの家はお金持ちではなく、普通のサラリーマン家庭だった)。
EXPO’70のテーマは「人類の進歩と調和」だった。そんな明るい未来を象徴するパビリオンが居並ぶ会場のど真ん中に、岡本太郎は、丹下健三設計のスタイリッシュな大屋根を突き破るようにして、太陽の塔を作った。頂点には黄金の仮面、正面には赤い炎に抱かれた歪んだ顔、裏には黒い不気味な顔があったが、どの顔も笑っていなかった。むしろ、明るい未来とは逆行するような、呪術的なパワーを発散していた。彼独特のEXPO’70へのアンチテーゼだった。
一方、岡本太郎は、太陽の塔の内部に、もうひとつの塔を作っていた。”生命の樹”である。のたうつ大木には、38億年の生命進化の流れが(今から思うとややチープな模型の三葉虫やアンモナイトが)貼り付けられていた。樹の頂点に位置するのは人間ではなく、単細胞生物だった。彼は生命の時間軸をも考えていたのだ。
EXPO’70は、約半年の会期に6400万人以上もの来場者を迎え、大成功裏に終わった。祭りの常として、終わると夢は幻のように姿を消した。パビリオン群はまたたく間に解体・撤去され、ただ太陽の塔だけが残された。
国際博覧会が初めて開催されたのは、1851年、ロンドンでのことだった。ハイド・パーク横に立ち上がったクリスタル・パレス(水晶宮)は人々の度肝を抜いた。鉄とガラスだけでできた巨大温室のような透明の伽藍。物珍しさから人々は争うようにやってきた。内部には、当時の最新技術や工業製品が展示され、中央広場には高い生木が立っていた。ときはヴィクトリア女王の治世。1837年に即位した若き女王は、その後60年以上の長きに渡って在位し、この間、大英帝国はその最盛期を迎えた。機械化が急速に進んだ。鉄道が敷設され、蒸気機関車が走り出した。製鉄技術が改良され、丈夫で粘り強い鉄鋼が量産された。つまり産業革命が勃興し、急速な経済成長が起きた。
安い資源、安い労働力、そしてより大きな消費地を求めて、大英帝国は拡大を開始した。すなわち7つの海に船を繰り出し、領土や植民地を獲得し始めた。
この政治経済的な動きと、文化的な機運が軌を一にした。人々の目がより広く世界の文物や自然に向けられるようになった。熱帯地域の美麗で稀少な鳥、植物、蝶、甲虫などの知識が求められた。富裕層は、博物学的な好奇心を持つようになり、家の居間に珍しい文物の調度品を飾ることが流行った。
チャールズ・ダーウィンが乗った英国艦船HMSビーグル号が出港したのは、ヴィクトリア女王戴冠の少し前、1831年12月のことである。
HMSとは、Her (His) Majesty
Ship、つまり女王(国王)陛下の艦船、という意味である。全長27.5メートル、排水量242トン、実戦が可能な大砲6門を搭載、英国精鋭の軍人70余名の船員が乗船する本格的な軍艦だった。
表向きの目的は、世界各地の自然環境の研究調査・測量だったが、その密かな狙いは、将来の世界展開に備えて、有望な軍事拠点を確認することだった。その証拠に、ビーグル号は、タヒチ、タスマニア、ココス、モーリシャスなど、今から見ると高級リゾート巡りをしているかのような航路をたどって、5年にわたる世界航海を行った。これら陸から離れた島々は、海運の中継点になり、地政学的にも重要な拠点となりえるからである。
『ビーグル号航海記』は、この世界航海の詳細な記録である。航海後に出版された、エキゾチックな未開の地をめぐる数々の物語は、博物学への関心が高まっていた当時の英国の人々の大評判を取った。そして『ビーグル号航海記』が、とりわけ有名にした島の名前がガラパゴスだった。ガラパゴスとはスペイン語でリクガメの意。甲羅の長さ1メートルを超える巨大なゾウガメが、そこら中を我が物顔に闊歩する不思議な島。南米エクアドルの太平洋上1000キロの赤道上に位置する絶海の孤島。
ひとくちに「ガラパゴス」といっても、そこは大小さまざまな島や岩礁が散在する群島である。名称がついている主要なものだけでも123島があると言われており、それがおよそ関東地方くらいの広い海域に分布している。
ダーウィンの乗ったHMSビーグル号は、1835年9月15日に、ガラパゴス海域東端のサン・クリストバル島(当時の英語名チャタム島)に到着した。英国を出港してから実に3年9か月が経過していた。当時、英国からガラパゴス島に行くためには、南米大陸の東側沿岸を南下し、大陸の南端マゼラン海峡をくぐり抜けて太平洋に出て、そこからさらにチリ沿岸を北上するという大航海が必要だった。ビーグル号は、ブラジルやフォークランド諸島、フエゴ島などで何度も寄港し、物資の補給とともに調査、測量を行っていたので、こんなに長い時間を要したのだった。ちなみに、フォークランド諸島やフエゴ島はその後、英国の領土となった場所である。
ダーウィンは、ガラパゴス島の荒涼たる様子をこんな風に書き記している。
「黒い玄武岩の溶岩がつくる、でこぼこの原野が、容赦なく打ち寄せる荒波の中に落ちこんでいる。大きな亀裂がいくつもあり、どこもかしこもひねて干上がった粗朶(そだ)に覆われていて、生命の気配はまるでない。真昼の太陽に灼かれる大地は乾いてパサパサしており、ストーブから受けるような息苦しい汗ばむような気分を、大気に与えていた」(荒俣宏訳、『ビーグル号航海記』平凡社)
チャサム島到着の後、約2か月をかけて、ガラパゴス諸島のうち、数少ない水源のある島、フロレアナ島(チャールズ島)、4つの大火山を擁するガラパゴス最大の島、イザベラ島(アルベマール島)、今も火山活動が激しい島フェルナンディナ島(ナーボロウ島)とのあいだの狭い海峡をくぐり抜けて、赤道線0度を越え、サンティアゴ島(ジェイムズ島)などに寄港し、調査と測量を行った。そして同年10月20日、次の調査地であるタヒチ島に向けて太平洋を西に進んだ。つまりビーグル号は1か月ほどをガラパゴス諸島の調査に費やした。
一般的には、このガラパゴス探検に着想を得たダーウィンが、のちの大著、『種の起源』を書きあげた、とされている。しかしそれはおそらく正確ではない。『種の起源』が書かれたのは1859年、ガラパゴスの旅から20年以上あとのことである。
ダーウィンはガラパゴス諸島の動植物、魚類などの標本を集め、本国英国に送り、また詳細な記録を残した。しかしそれはあくまで博物学的な、つまり網羅的な記録にとどまっていた。問題は、網羅しようにもしつくせない多様性だった。
何と言ってもダーウィンはまだ若かった。ビーグル号が出港した1831年暮には22歳、船がガラパゴスに到達したときでも26歳だった。しかもダーウィンは、海軍艦船ビーグル号の正式な乗組員ではなかった。船長フィッツロイの話し相手かつ客人として、たまたま便乗させてもらった。
エディンバラ大で医学を、ケンブリッジ大で神学を目指したものの、いずれも道半ばで挫折していたダーウィンの将来を心配した父親が、博物学好きの、いささか変わり者の息子の可能性を広げるチャンスとして、コネをつかって押し込んだ、というのが真相だ。
ダーウィンの心の中にはまだ何も準備ができていなかった。
しかし、ガラパゴスの奇妙すぎる自然は、英国しか知らなかったダーウィンを驚かせるに十分すぎた。ダーウィンはガラパゴス島に生息する不思議な生物たちに目を見張った。あちこちを悠然と闊歩する巨大なゾウガメ、陸地と海辺に分かれて生活するオオトカゲのイグアナ、人を恐れることを知らない鳥たち……生命はなぜ、かくも自由奔放で、かつ多種多様に生を全うすることができるのだろうか。
おそらくダーウィンの心の中に、ひとつだけキーワードが浮かび上がっていたにちがいない。それは「時間」である。
それまで世界に与えられていた時間は、長いようでいて短いものだった。せいぜい数千年。その出発点においては神さまがすべての多様性を創造した。人間のために。これが、長年にわたって人々が信じ込んでいた物語だった。ダーウィンは何とかして、ここに神さまを持ち出さずに、世界の多様性を説明したいと願った。もし、十分すぎるほどの時間さえあれば、生命は自発的に変化し、自発的に選択され、その結果として多様性が実現されるのではないだろうか。生物たちの多様性と環境に対する巧みな適応が、生物の「進化」によって達成されたと考える、いわゆる進化論の着想と構築にはここから先、長い長い思索の時間が必要だった。
『ビーグル号航海記』を読んで、私は思った。いつか私も、ダーウィンと同じ航路をたどって、彼が見たであろう光景を、彼が見たはずの順番で、この目で見て確かめてみたい。いったいガラパゴスの何が、彼の目を見開かせ、彼の想像力を掻き立てたのだろう。それを追体験したかった。これは、若い頃の私の、ほとんど非現実な夢想だったが、あとになってほんとうに実現することになった。そのことをここで書き出すと話が終わらなくなるので、また別の機会に筆を譲りたいと思う。
さて、万博の話にもう一度戻ろう。19世紀なかば、最初の万博がロンドンで開かれた背景には、人々の目が世界に向けられたことがある。そして世界が示す多様性が、博物学的な関心を呼び起こすことにつながり、そしてその多様性を説明するセオリーが求められることにつながった。ダーウィンの『ビーグル号航海記』、そしてその後20年をかけて構築された進化論は、まさにそれに答えるセオリーとなった。
万博はその後、世界各地で開催され、科学的な思考、テクノロジーとイノベーションの啓発と普及に大きな役割を果たした。戦後の高度経済成長期の頂点の日本で、EXPO’70は開催された。
以来50年余り。現在の私たちは、EXPO’70が約束したはずの「人類の進歩と調和」の中にはいない。進歩と調和の代わりに、停滞と分断のはざまにいる。地震や異常気象、大事故やテロに苛まれた。原発事故が起き、広範囲の土壌が汚染された。経済は停滞し、日本の人口は少子高齢化が進んだ。人種、民族、国家、文化が対立し、ネット社会が人々の分断を加速している。その上、出口が見えないコロナパンデミックの真っ只中にある。
私たちは今、あらゆることに不審と不満をかかえている。それは一体なぜだろうか。それは、コロナ禍があぶりだしたとおり、政治も、経済も、端的に言って、その根本のところで、生命に対する基本的な向き合い方が定まっていないからである。膨大な時間をかけて、変化し、選択され、多様性を花開かせた生命の価値と意味に対する”哲学”が見えないからである。図らずも、EXPO2025のテーマは「いのち」である。私にかせられた課題は、ポストコロナの生命哲学を明示することだと考えている。
新訳 ビーグル号航海記〈上〉〈下〉

(著者) チャールズ・R.ダーウィン著/荒俣宏訳
(出版社)平凡社
(価格)〈上〉2300円+税、〈下〉2400円+税